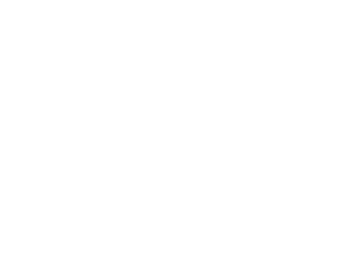- 樹木葬
お彼岸・お盆にどう過ごす?樹木葬でのお参りスタイル
第1章 お彼岸・お盆はいつ?どんな意味があるの?
お彼岸やお盆は、日本で古くから続く大切な供養の行事です。どちらもご先祖様や故人を想い、感謝を伝えるための機会ですが、時期や背景、行う理由にはそれぞれ違いがあります。まずはその意味と由来、一般的な過ごし方を知ることで、お参りの心構えを整えましょう。
お彼岸とは
お彼岸は、春と秋の年2回訪れます。春分の日・秋分の日を中日(ちゅうにち)として、前後3日間、計7日間が「お彼岸」の期間です。春は3月20日前後、秋は9月23日前後になることが多いですが、年によって日付が変わります。
お彼岸は仏教に由来し、「彼岸」とは仏の悟りの境地を意味します。私たちが生きているこの世を「此岸(しがん)」と呼び、彼岸はその向こう側にある安らぎの世界を指します。春分・秋分の日は昼と夜の長さがほぼ同じになり、太陽が真西に沈むことから、西方浄土への道が開け、ご先祖様と心を通わせやすい日とされてきました。
お彼岸には、仏壇やお墓をきれいに掃除し、花やお供え物を用意してお参りをするのが一般的です。家庭によっては、ぼたもち(春)やおはぎ(秋)を作って供える習慣もあります。
お盆とは
お盆は、地域によって時期が異なりますが、全国的には7月または8月に行われます。もっとも一般的なのは8月13日〜16日の4日間で、「旧盆」と呼ばれます。一方、都市部などでは7月に行われる「新盆(しんぼん)」の地域もあります。
お盆は、ご先祖様の霊を家に迎え入れ、再び送り出す行事です。仏教行事と日本古来の祖霊信仰が融合してできたといわれ、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼びます。初日は迎え火を焚き、ご先祖様をお迎えし、期間中は仏壇や精霊棚にお供えをして過ごします。最終日には送り火で見送り、元の世界へとお帰りいただきます。
お盆は家族や親族が集まり、故人を偲ぶ機会でもあります。特に初めて迎えるお盆を「初盆(はつぼん)」と呼び、親族や知人を招いて法要を営むこともあります。
お彼岸とお盆の違い
お彼岸は年2回、ご先祖様と心を通わせる仏教由来の行事で、季節の節目としても意味があります。一方、お盆は年1回、ご先祖様を家に迎える日本独自の行事です。お彼岸はお墓参りが中心であるのに対し、お盆は家での供養や親族の集まりが重視される傾向にあります。
樹木葬との関わり
樹木葬でも、お彼岸やお盆にお参りする習慣は大切にされています。従来の墓石の代わりに樹木や草花を墓標とするため、墓前の掃除やお供えの方法が少し異なる場合がありますが、「ご先祖様を偲ぶ」という根本の想いは変わりません。
お彼岸やお盆の意味や過ごし方を理解することで、樹木葬でも心のこもった供養ができます。次の章では、樹木葬ならではのお参りスタイルについて詳しく見ていきます。
第2章 樹木葬ならではのお参りスタイル

樹木葬は、従来のお墓と異なり、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする自然葬の一種です。緑豊かな環境の中で眠ることができ、近年は「自然に還る」という考え方や、維持管理のしやすさから選ぶ方が増えています。しかし、墓所の形態が異なるため、お彼岸やお盆にお参りする際のスタイルやマナーにも特徴があります。
樹木葬のお参りの基本
樹木葬でのお参りは、一般的なお墓参りと同じく「故人を偲び、感謝を伝える時間」であることに変わりはありません。ただし、墓標が石ではなく樹木や草花のため、以下のような違いがあります。
・お掃除の仕方
墓石の拭き掃除や水かけではなく、周囲の落ち葉や雑草を取り除く程度で済む場合が多いです。施設によっては管理者が定期的に手入れを行うため、訪問時の掃除は簡易的で構いません。
・お花やお供物の扱い
樹木葬では「自然との調和」を重視するため、造花やラッピング材、プラスチック容器は避けるよう求められることがあります。生花を持参する場合は、持ち帰りルールや指定の供花台の有無を事前に確認しましょう。食べ物のお供えも野生動物を呼び寄せる恐れがあるため、禁止している墓所も少なくありません。
・線香やろうそくの使用
樹木や芝生への延焼防止のため、火気の使用が制限される場合があります。その場合は、管理事務所で用意された献花スペースや屋内祭壇を利用します。
季節行事との関わり
お彼岸やお盆の時期は、多くの人が墓所を訪れるため、駐車場やアクセス路が混雑することがあります。樹木葬は公園型や里山型など広い敷地にあるケースが多く、自然を感じながらゆったり過ごせる一方で、暑さ寒さや天候への配慮も必要です。特にお盆の時期は日差しが強いため、日傘や帽子、飲み物などの暑さ対策を忘れずに行いましょう。
服装や持ち物の工夫
従来の墓地では正装や黒を基調とした服装が一般的ですが、樹木葬では自然の中を歩くため、動きやすい服装や歩きやすい靴が望まれます。ただし、お彼岸やお盆のような正式な行事では、カジュアルすぎない清潔感のある服装を心がけると安心です。
マナーと注意点
樹木葬では、個々のお墓が小さなプレートや石碑、または区画全体で管理されている場合があります。そのため、他の区画や植栽を踏み荒らさないよう注意しながら参拝します。また、自然環境を守るため、ゴミや枯れた花は必ず持ち帰るのが基本です。
施設によってはペット同伴可の場合もありますが、リード着用や排せつ物の持ち帰りが必須です。反対に、ペット不可の墓所もあるため事前確認が必要です。
樹木葬ならではの魅力
樹木葬は、墓前で合掌するだけでなく、周囲の自然を楽しみながら故人を偲ぶことができます。鳥の声や風の音、季節ごとに変わる花や葉の色が、参拝そのものを豊かな時間にしてくれます。お彼岸やお盆に訪れると、春は桜や新緑、秋は紅葉や澄んだ空気の中で、より深い供養の時間を過ごせます。
次の章では、この特長を踏まえた「お彼岸・お盆におすすめの樹木葬お参り方法」について、具体的な手順や持ち物リストを交えてご紹介します。
第3章 お彼岸・お盆におすすめの樹木葬お参り方法

樹木葬でのお参りは、自然との調和を大切にしながら、故人を偲び感謝を伝える時間です。お彼岸やお盆は特に多くの方が訪れるため、事前準備やマナーを押さえておくことで、より穏やかで心のこもった供養ができます。ここでは、樹木葬に適したお参りの手順や持ち物、服装などを具体的にご紹介します。
1. 事前準備とスケジュール確認
お彼岸(春・秋)やお盆は混雑が予想されるため、可能であれば平日や午前中の訪問がおすすめです。駐車場の有無やアクセス方法、受付時間を事前に確認しましょう。また、樹木葬の墓所には火気使用禁止やお供物制限など独自のルールがあるため、公式サイトや管理事務所に事前問い合わせをしておくと安心です。
2. 持ち物の準備
樹木葬では、自然環境を守るため持ち物にも配慮が必要です。以下はおすすめの持ち物リストです。
・生花(自然分解できるもの)
季節の花や故人の好きだった花を選びます。ラッピング材やビニールは現地で外して持ち帰ります。
・お供物(施設のルールに応じて)
食べ物は動物を呼び寄せるため禁止の場合が多いです。許可されている場合も、すぐに下げるのがマナーです。
・掃除道具(簡易的なもの)
軍手、ハサミ、小さなほうきやちりとり。落ち葉や雑草取りに使います。
・合掌・焼香用の道具
火気使用可の施設なら線香・ろうそくを、不可の場合は献花や静かな黙祷で代替します。
・天候・季節対策グッズ
日傘、帽子、飲み物、防寒具、雨具など。
3. お参りの手順
樹木葬でのお彼岸・お盆参拝は、一般的なお墓参りと大きく変わらない流れですが、自然葬ならではの配慮を加えることでより心地よい時間になります。
1.到着後の挨拶
墓所に到着したら、まず周囲に一礼し、故人への訪問の挨拶を心の中でします。
2.墓所周りの清掃
樹木やプレート周辺の落ち葉や雑草を取り除きます。樹木の幹や葉には触れすぎないよう注意します。
3.お花やお供物の準備
花立や供花台にお花を飾ります。お供物は必要に応じてすぐ下げられるようにします。
4.焼香・合掌
火気が使えない場合は、静かに手を合わせ、感謝や近況報告を心の中で伝えます。
5.帰りの挨拶と片付け
使用した道具やお供え物、ゴミは必ず持ち帰り、最後に一礼して墓所を後にします。
4. 服装のポイント
樹木葬は自然の中を歩くため、動きやすく清潔感のある服装が望まれます。お彼岸やお盆といった年中行事では、あまり派手すぎない落ち着いた色味を選びます。特にお盆法要や合同供養祭に参加する場合は、黒やグレーなどのフォーマル寄りの服装が安心です。靴は芝生や土の上でも歩きやすいものを選びましょう。
5. 心のこもった供養のために
お彼岸やお盆は、ご先祖様や故人を偲ぶ大切な機会です。ただ形だけ整えるのではなく、「ありがとう」の気持ちや故人との思い出を振り返る時間を持つことが一番の供養になります。樹木葬では、その場の自然や四季の変化が供養の背景となり、より深い癒やしやつながりを感じられるでしょう。
次の章では、こうしたお参りを長く続けるための「心を込めた供養を続ける工夫」についてご紹介します。日常生活の中でできる小さな供養や、遠方からでも気持ちを届けられる方法も解説します。
第4章 心を込めた供養を続けるための工夫

お彼岸やお盆は年に数回の特別な行事ですが、供養はその時だけに限られるものではありません。樹木葬の場合、自然に囲まれた墓所だからこそ、日常の中でも心を寄せ、長く続けられる供養の工夫があります。ここでは、季節ごとの訪問や遠方からの供養方法、現代ならではのサービス活用など、心を込めた供養を続けるためのヒントをご紹介します。
1. 季節ごとのお参りを楽しむ
お彼岸やお盆以外でも、春夏秋冬の景色に合わせて訪れるのもおすすめです。
・春:新緑や花の芽吹きとともに、生命力を感じながらお参り。
・夏:木陰や草花の香りが心地よい季節。暑さ対策をしてゆっくり過ごす。
・秋:紅葉や落ち葉の色づきが墓所を彩り、静かな雰囲気で供養できる。
・冬:雪景色や枯れ木の静寂もまた故人を偲ぶ落ち着いた時間に。
樹木葬では、季節の移ろいがそのまま供養の背景になるため、訪れる時期ごとに新たな思い出を重ねられます。
2. 遠方からでもできる供養
仕事や生活の都合で頻繁に訪問できない場合でも、心を込めた供養は可能です。
・お参り代行サービスの利用:管理事務所や提携業者が花を供え、清掃をしてくれるサービスがあります。写真や報告書で様子を確認できるため安心です。
・オンライン供養:最近ではビデオ通話やライブ配信でお参りできる施設もあります。離れていてもリアルタイムで祈りを捧げられます。
・記念日のお供え注文:命日や誕生日などに合わせて花やメッセージを届けるサービスもあります。
3. 日常の中でできる小さな供養
必ずしも墓所に行かなくても、日常生活の中で故人を想う時間を持つことが大切です。
・仏壇や写真立てに花を飾る
・故人が好きだった音楽や料理を楽しむ
・季節の行事を思い出とともに過ごす
こうした小さな習慣が、日々の暮らしに自然と供養の心を根付かせます。
4. 家族や友人と共有する
供養は個人だけでなく、家族や友人と一緒に行うことで、より温かみのある時間になります。お彼岸やお盆に合わせて親族で集まり、樹木葬の墓所を訪れるのもよいでしょう。写真を撮ってアルバムに残すことで、供養の記録としても価値が高まります。
5. 自然環境を守る意識
樹木葬の魅力は、故人が自然と一体になれることです。その環境を長く守るために、参拝時には環境負荷を減らす行動を心がけましょう。ゴミを持ち帰る、生分解性の花材を使う、禁止されている行為(火気、ペット無許可同伴など)を避けるなど、ルールの遵守が大切です。
お彼岸やお盆といった節目は、供養の大切さを再認識する機会ですが、本当の意味での供養は日常の積み重ねにあります。樹木葬は自然とのつながりを感じやすく、四季折々の景色とともに故人を偲べる場所です。季節ごとに訪れる、遠方からでも心を寄せる、小さな習慣を大事にする――こうした積み重ねが、故人とのつながりを深くし、自分自身の心も穏やかにしてくれるでしょう。
佐藤石材では、公営霊園実績多数!神奈川県・東京都公営霊園・墓地・寺院にて施工を承っております。

佐藤石材は、峰山霊園、大庭台墓園、清川村宮ヶ瀬霊園、相模原市営柴胡ケ原霊園のお墓建立実績多数!
ご予算内でお客様のご希望に合わ せたオリジナル彫刻墓石をおつくりします
故人様の思い出や趣味の写真、故人様への思いや言葉を彫刻いたします。
佐藤石材は、ご予算内の安心価格で、ご要望に応じたデザインと耐久性を兼ねそろえた墓石をおつくりします。代表の佐藤は、日本石材産業協会お墓ディレクター 2級を取得しておりますので、様々な石の特長を把握しております。お客様の好みや、墓地の風土、ご予算に合わせて様々な石種をご提案することが可能です。当社では、「できません」とはなるべく言わないように心がけております。できる方法を考え、ご提案させていただきます。また、お見積り時には安心してご契約頂けるように、3Dのイメージ図と設計図を必ずお見せしますのでご安心ください。