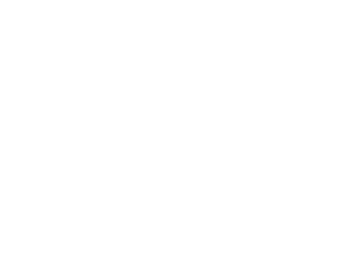- 選び方で後悔をしない!必見情報
納骨当日の流れ:持ち物・所要時間・写真撮影の可否と配慮
第1章:納骨当日の流れをわかりやすく解説
納骨とは、火葬を終えたご遺骨をお墓や納骨堂に納める儀式のことを指します。葬儀が「故人を見送るための儀式」であるのに対し、納骨は「故人の魂を安らかに供養するための大切な節目」です。多くの方にとって一生に何度も経験することではなく、「当日はどんな流れで進むの?」「何を準備しておけばいいの?」と不安を感じるのも当然です。今回は、納骨式の一般的な流れ等をわかりやすく解説します。
1. 納骨式当日の基本的な流れ
納骨式は、宗派や地域、埋葬する場所(寺院墓地・公営霊園・民営霊園など)によって多少の違いはありますが、一般的には以下のような順序で行われます。
1)参列者の集合・受付
当日は、施主や家族、親族、親しい知人が集まります。集合場所は寺院の本堂前や霊園の管理棟などが多く、開始の15〜30分前には到着しておくのが望ましいです。
受付では、香典や供物を渡す場合もありますが、納骨式のみの場合は不要なこともあります。服装は喪服または控えめな平服で、黒や紺など落ち着いた色を選びましょう。
2)僧侶による読経と焼香
本堂や墓前にて僧侶(または神職)が読経を行い、参列者が順番に焼香します。読経の時間は10〜20分程度が一般的で、宗派によって経典や所作が異なります。僧侶へのお布施は事前に準備し、袱紗(ふくさ)に包んで渡します。
3)納骨(ご遺骨をお墓へ納める)
読経が終わると、墓前でご遺骨を納めます。多くの場合、骨壺を墓石の下にある納骨室(カロート)へ安置し、墓石を閉じた後に花や線香を手向けます。
このとき、墓石の開閉や骨壺の設置は霊園スタッフや石材店が行うことが多いため、施主は指示に従えば問題ありません。
4)僧侶の法話・施主の挨拶
納骨が終わると、僧侶から短い法話をいただくことがあります。その後、施主(または代表者)が参列者に感謝の挨拶を述べて、式は終了します。
2. 納骨式の全体所要時間
納骨式の所要時間は、読経・焼香・納骨・挨拶を含めておおよそ60〜90分程度が一般的です。墓前ですと30分で終わるケースもあります。
移動を伴う場合(本堂で法要を行ってから墓地に移動するなど)は、合計で2時間程度を見ておくと安心です。
また、納骨後に「精進落とし(会食)」を行うことも多く、その場合は全体で半日ほどかかることもあります。遠方からの参列者がいる場合は、スケジュールに余裕を持たせましょう。
3. 宗派や埋葬場所による違い
仏教では僧侶による読経が中心ですが、神道では神職による「納骨祭」として玉串奉奠(たまぐしほうてん)が行われます。キリスト教では牧師や神父による「納骨式(埋葬式)」となり、聖書朗読や祈りが中心です。
また、最近では宗教色を控えた「無宗教葬」や「家族だけの静かな納骨」も増えています。霊園によっては僧侶の手配を代行してくれる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
4. 納骨当日をスムーズに進めるためのポイント
・事前確認を忘れずに
埋葬許可証や骨壺の準備、僧侶への依頼、霊園の立ち会い時間など、前日までに確認しておきましょう。
・天候対策も重要
屋外で行うため、雨天時の傘や靴の準備も必要です。
・心の準備を整えて
納骨は故人を「お墓に迎える」大切な儀式です。焦らず、心静かに臨むことが何より大切です。
納骨式は、「形式をこなす儀式」ではなく、故人の魂を安らかに弔い、家族が新たな一歩を踏み出すための大切な時間です。
全体の流れを理解し、持ち物やマナーを整えておけば、慌てることなく穏やかな気持ちで当日を迎えられるでしょう。
第2章:納骨当日に必要な持ち物と服装マナー

納骨式は、故人をお墓にお迎えする大切な儀式です。当日を穏やかに迎えるためには、事前の準備がとても重要です。
「何を持っていけばいいの?」「服装は喪服でなければいけないの?」と悩む方も多いですが、実際には宗派や場所、参列者の範囲によって多少の違いがあります。ここでは、納骨式に必要な持ち物と、恥ずかしくない服装マナーを詳しく解説します。
1. 納骨式に必要な持ち物リスト
納骨当日に必要な持ち物は、大きく「必須のもの」と「用意しておくと安心なもの」に分けられます。
【必須の持ち物】
・骨壺(ご遺骨)
納骨式の主役ともいえる大切なものです。骨壺が2つ以上ある場合(分骨など)は、霊園や寺院に事前に確認しておきましょう。
・埋葬許可証
火葬後に発行される「埋葬許可証」は、納骨の際に必ず提出が必要です。これがないと納骨できない場合がありますので、忘れずに準備してください。
・位牌(いはい)・遺影(いえい)
本堂での法要を行う場合に使用します。墓前のみの納骨の場合は、持参しないケースもあります。
・お布施
僧侶に読経をお願いする場合は、お布施を用意しましょう。金額の目安は1〜3万円程度。白封筒または水引きの「御布施」袋に入れ、袱紗(ふくさ)に包んで渡します。
・数珠
仏式の納骨では必ず持参します。宗派ごとに数珠の形が異なる場合もありますが、一般的な略式数珠でも問題ありません。
【あると便利な持ち物】
・線香・ろうそく・ライター
霊園によっては用意がない場合があります。
・供花・供物
花は白や淡い色が無難です。果物や故人の好物をお供えする方も多いです。
・タオル・ハンカチ・ティッシュ
屋外での儀式は汗や涙を拭く場面も多いものです。
・雨具(折りたたみ傘・滑りにくい靴)
天候が変わりやすい季節は特に忘れずに準備しましょう。
2. 服装マナー:喪服?それとも平服で大丈夫?
納骨式の服装は、「葬儀よりは控えめ」「清潔で落ち着いた装い」が基本です。
【施主・遺族の場合】
喪服(ブラックフォーマル)を着用するのが一般的です。男性は黒のスーツ、白シャツ、黒ネクタイ。女性は黒のワンピースまたはスーツに黒いストッキング、バッグも黒を選びます。靴は金具のないプレーンなタイプを。
【親族・参列者の場合】
遺族より少し控えめな「準喪服」「地味な平服」で問題ありません。黒・グレー・紺など、落ち着いた色のスーツやワンピースを選びましょう。
特に最近は、家族葬後の納骨が多く、堅苦しくない雰囲気の式も増えています。施主が「平服で」と伝えている場合は、その意向を尊重しましょう。
【季節・天候への配慮】
・夏は薄手の黒やグレーの服装でもOKですが、派手な素材や露出は避けましょう。
・冬は黒やグレーのコートで問題ありません。ファーや光沢のある素材は避けるのがマナーです。
・雨天時は滑りにくい靴やレインコートを用意し、霊園の通路が濡れても安全に移動できるようにしましょう。
3. 子どもや高齢者の服装と準備
子どもが参列する場合は、黒や紺など落ち着いた色の服を選びましょう。学生服でも構いません。
高齢の方は足元が滑りやすい場合があるので、歩きやすい靴を優先するのが安心です。特に墓地は段差が多いため、杖や折りたたみ椅子を持参する方もいます。
4. 当日のマナーと心得
・香水やアクセサリーは控えめに
・携帯電話は電源を切るかマナーモードに
・写真撮影を行う場合は必ず施主に確認を
・故人や家族の思いを尊重し、静かで落ち着いた態度を心がけましょう
納骨式は、華やかさよりも「故人への思いやり」「落ち着いた所作」が大切です。
必要な持ち物を前日までに準備し、服装を整えておけば、当日慌てることなく心静かに臨むことができます。
そして、形式よりも気持ちを込めて手を合わせることこそが、何よりの供養になるのです。
第3章:納骨式にかかる所要時間とスケジュール管理

納骨式は、葬儀と比べて規模は小さいものの、心を込めて行う大切な儀式です。
当日の流れを把握しておくことで、慌てることなく落ち着いて行動でき、参列者への配慮もしやすくなります。
ここでは、納骨式にかかる所要時間の目安や、スムーズに進めるためのスケジュール管理のポイントを詳しく解説します。
1. 納骨式全体の所要時間の目安
納骨式の全体所要時間は、おおよそ60〜90分程度が一般的です。
ただし、式の内容や場所によって前後するため、事前に確認しておくことが大切です。
【一般的な所要時間の目安】
・参列者の集合・受付:15〜20分
・僧侶の読経・焼香:15〜30分
・納骨(ご遺骨の安置・お参り):20〜30分
・施主の挨拶・解散:5〜10分
このように、法要からお墓への移動を含めると、平均して1時間半前後になります。
寺院の本堂で読経を行ってから墓前に移動する場合は、その移動時間(5〜10分)を含めると2時間程度を見ておくと安心です。
2. 当日のスケジュール例
納骨式は、午前または午後の早い時間に行われることが多く、以下のような流れが一般的です。
【納骨式のスケジュール例(午前開催の場合)】
|
時間 |
内容 |
|
9:30 |
施主・家族が現地到着、受付・準備 |
|
9:45 |
参列者集合、僧侶・霊園スタッフと打ち合わせ |
|
10:00 |
本堂で読経・焼香 |
|
10:30 |
墓前へ移動し納骨 |
|
11:00 |
花・線香を供えて合掌、僧侶の法話 |
|
11:15 |
施主の挨拶・集合写真など |
|
11:30 |
解散または会食会場へ移動 |
午後からの場合は、同様の流れで13時〜15時頃に行うケースが多いです。
霊園によっては17時以降の納骨を受け付けない場合もあるため、必ず事前に確認しておきましょう。
3. 所要時間が長引くケースと短縮されるケース
納骨式の所要時間は、いくつかの要因で変わります。
⏱ 所要時間が長くなるケース
・僧侶による法話やお経が長めに行われる
・本堂と墓地が離れており、移動に時間がかかる
・参列者が多く、焼香の列が長くなる
・会食(精進落とし)を当日に行う
⏱ 短縮されるケース
・家族のみ・無宗教形式で簡素に行う
・納骨堂での納骨(移動が少ない)
・僧侶を呼ばず、黙祷のみで行う
特に最近では、家族葬の延長として「家族だけで静かに納骨する」スタイルが増えており、30〜45分ほどで終わるケースも少なくありません。
4. スムーズに進めるためのスケジュール管理のコツ
納骨式を滞りなく行うためには、時間配分だけでなく、事前準備と関係者との連携が欠かせません。
【事前準備のチェックポイント】
・霊園・寺院に開始時間と所要時間の目安を確認
・僧侶や神職に読経・法要の内容と時間を相談
・参列者に集合時間・場所・服装を事前に連絡
・雨天時の対応(テントの有無・傘の準備)を確認
また、施主は当日、式の進行や挨拶に集中できるよう、石材店や霊園スタッフに進行補助を依頼しておくと安心です。
霊園によっては、花の手配や骨壺の搬入を代行してくれるサービスもあります。
5. 高齢者・子どもが参列する場合の時間配慮
小さなお子さんや高齢者が参列する場合は、長時間の屋外での儀式が負担になることもあります。
できるだけ午前中や涼しい時間帯を選び、移動時間を短くするのが望ましいでしょう。
また、途中で休憩できるスペースや椅子を用意しておくと安心です。
納骨式の時間は決して長くはありませんが、故人を想い、心を整える貴重なひとときです。
時間配分に余裕を持って準備すれば、焦ることなくゆったりとした気持ちで臨むことができます。
当日のスケジュールをしっかり把握し、参列者が安心して参列できるような配慮を心がけましょう。
納骨の一日を穏やかに過ごすことが、何よりの供養となるのです。
第4章:写真撮影の可否と、故人・参列者への配慮

納骨式は、故人をお墓にお迎えし、ご家族が心を込めて手を合わせる大切な儀式です。
そのため、「当日の様子を記録に残したい」「お墓を建てた記念に写真を撮りたい」と考える方も少なくありません。
しかし、納骨式は宗教儀式であり、厳粛な場面が多いため、撮影の可否には慎重な配慮が求められます。ここでは、写真撮影を行う際のマナーや注意点、心配りのポイントを詳しく解説します。
1. 納骨式で写真撮影はしてもよいのか?
基本的に、納骨式での写真撮影は「禁止ではないが、確認が必要」です。
撮影が許可されるかどうかは、行う場所(寺院・霊園・納骨堂)や宗派によって異なります。
たとえば、寺院では「読経中や焼香中の撮影はご遠慮ください」としていることが多く、儀式の妨げにならないよう求められます。
一方で、公営・民営霊園などでは、墓前での記念撮影を許可している場合もあります。
したがって、撮影を希望する場合は、必ず事前に寺院や霊園の管理事務所に確認しておきましょう。
2. 撮影してよい場面・控えるべき場面
撮影する際は、「厳粛な儀式を妨げないこと」「参列者の気持ちを大切にすること」が基本です。
以下を参考に、適切なタイミングを判断しましょう。
【撮影してよい場面】
・納骨が終わり、僧侶の読経が終了したあと
・墓石や花、お供え物を撮影する時
・参列者全員で集合写真を撮る時(施主が許可した場合)
・新しく建立したお墓の記録を残す時
【控えるべき場面】
・僧侶が読経している最中
・焼香や納骨の最中
・遺骨や骨壺を扱っている場面
・故人や参列者が涙している場面
これらの時間帯は、儀式の中心であり、静寂が求められます。
カメラのシャッター音やフラッシュが雰囲気を損なう恐れがあるため、できるだけ式の終了後に撮影するのが無難です。
3. 撮影時のマナーと心配り
撮影を行う際は、形式やマナー以上に「心遣い」が大切です。
特に以下の3つを意識すると、トラブルを防ぎつつ、穏やかな雰囲気を保つことができます。
1)必ず施主(喪主)に撮影の許可を取る
たとえ自分の家族であっても、施主の意向を確認するのが礼儀です。
「記念に1枚撮ってもよろしいでしょうか?」と一言添えるだけで印象が大きく変わります。
2)撮影は控えめに・短時間で
儀式の進行を妨げないよう、写真は必要最低限にとどめましょう。
長時間の撮影やポーズの指示は避け、静かに行うことが大切です。
3)SNS投稿は慎重に
撮影した写真をSNSに投稿する場合は、参列者の顔や個人情報が写っていないか必ず確認しましょう。
また、寺院や霊園の敷地内の写真を公開する場合も、許可が必要なケースがあります。
「供養の記録」を残すことと、「他者に見せること」は意味が異なる点を意識しましょう。
4. 記録を残すなら「心で残す」ことも大切に
納骨式の記録を残すことは悪いことではありませんが、何より大切なのは「その場に心を寄せること」です。
写真を撮ることに夢中になってしまうと、故人を偲ぶ気持ちや静かな時間が薄れてしまうことがあります。
もし記念を残したい場合は、式の後にお墓や供花を静かに撮影することで十分です。
また、最近では「納骨記念フォト」を専門に撮影するカメラマンサービスも登場しています。
プロに依頼すれば、マナーを守りながら自然な雰囲気で撮影してもらえるため、施主の負担を軽減できます。
ただし、依頼する際は必ず寺院・霊園側に撮影の可否を確認しておきましょう。
納骨式での写真撮影は、禁止ではありませんが「節度と配慮」が欠かせません。
故人への敬意、参列者の気持ち、そして場の空気を大切にすることが最も重要です。
写真はあくまで記録として、主役は「故人への祈り」であることを忘れずに。
カメラのレンズ越しではなく、心の中に故人の姿をしっかりと刻む——
それこそが、何よりの供養であり、後に残る温かい思い出になるでしょう。
佐藤石材では、公営霊園実績多数!神奈川県・東京都公営霊園・墓地・寺院にて施工を承っております。

佐藤石材は、峰山霊園、大庭台墓園、清川村宮ヶ瀬霊園、相模原市営柴胡ケ原霊園のお墓建立実績多数!
ご予算内でお客様のご希望に合わ せたオリジナル彫刻墓石をおつくりします
故人様の思い出や趣味の写真、故人様への思いや言葉を彫刻いたします。
佐藤石材は、ご予算内の安心価格で、ご要望に応じたデザインと耐久性を兼ねそろえた墓石をおつくりします。代表の佐藤は、日本石材産業協会お墓ディレクター 2級を取得しておりますので、様々な石の特長を把握しております。お客様の好みや、墓地の風土、ご予算に合わせて様々な石種をご提案することが可能です。当社では、「できません」とはなるべく言わないように心がけております。できる方法を考え、ご提案させていただきます。また、お見積り時には安心してご契約頂けるように、3Dのイメージ図と設計図を必ずお見せしますのでご安心ください。